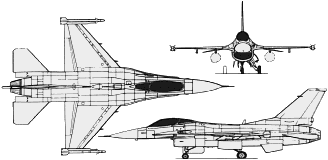
1972年、米空軍は国内の航空機メーカー9社に対し、LWF(軽量戦闘機)計画と呼ばれる新戦闘機の設計提案を求めた。その時、各社へ配られた仕様書はわずか21頁のものであり、これは細かな要求が独創性や斬新な設計を妨げることなく、最新の空力および材料技術を思う存分導入させようという配慮からだ。結果、最終審査で残ったのはジェネラルダイナミックス案(YF-16)とノースロップ案(YFー17)で、飛行審査のため、それぞれ2機づつの試作機が製作される。 YF-16の1号機は1974年2月2日、YF-17の1号機が同年6月9日に初飛行を遂げ、この時点で米空軍はまだLWFの採用を決めていない。あくまで未来の戦闘機図を模索する実験的性格が強く、また平行してマクダネルダグラスF-15イーグルの導入を進めているところでもあった。しかし、F-15は高価な買物であり、そこへ安価な戦闘機を併用させる動きが米議会で出始め、これを「ハイ・ロー・ミックス構想」という。 1974年、米空軍はLWF実施計画を発表し、がぜん勢いづく。1975年1月、熾烈な飛行審査の後、ジェネラルダイナミックス社へ軍配が下りると同時、米空軍は650機のF-16導入計画を発表する。また、敗者となったノースロップ社が全力でNATO四空軍の次期戦闘機にF-17を、あるいはミラージュF1の政治絡みの売り込みを退け、同月、F-16はヨーロッパからも376機の大量注文を獲得したのだ。 この決定で、生産への配慮が大きく作用している。最新の空力や材料技術の導入ばかりか、F-16は現地生産を考慮して開発された。ヨーロッパ各国の航空機産業が生産へ参加できるメリットは魅力であり、単価が約500万ドルと安価な上、その多くは地元に落ちるのである。日本の航空自衛隊がF-15を採用し、ライセンス生産を始めた時、メーカーである三菱の本音は、手出しの出来ない米国からの輸入部品が多いF-15は(単価が倍以上するにもかかわらず)自社生産工程の多いF-16より儲からないということだった。 F-16で採り入れられた新技術は多く、外形上まず目を引くのが、翼と胴体を一体形成し、互いの干渉抵抗を減少させるブレンデッド・ウィング・ボデーだ。機首側面から主翼前縁付根へのストレークも、大仰角時の性能を引き上げている。胴体下部の空気取入口はシンプルそのもので、姿勢による空気流入量の変化へ敏感なターボファン・エンジンにとって都合がいい。そのエンジンもF-15と共通のF100を採用したことは、米空軍の採用へ少なからず貢献しているだろう。 高度な空戦性能を持たせるため機体強度が増し、量産型のF-16は9Gに耐えうる。搭乗員へかかる高Gを配慮した結果、30度傾けた座席と短い操縦桿が右コンソール上につき、実用軍用機では初のサイドスティックだ。空中戦で良好なコクピット視界を確保すべく一体形成のキャノピーは枠がない。 空戦を重視する一方で、対地攻撃能力もおろそかにされなかった。ハードポイント(機外の兵装搭載箇所)9ケ所のうち4ケ所へは空対空ミサイル、残る5ケ所に空対地ミサイル、爆弾、燃料タンクなどが搭載できる他、左主翼付根にはバルカン砲1門が固定装備されている。 これらの兵器は高性能の火器管制装置が自動的にコントロールし、データは正面のHUD(ヘッド・アップ・ディスプレイ)へ各モードで表示され、火器管制装置の目となるのが機首に装備されたAPG-66レーダーだ。外観からは想像できないほど優れた機能のパルス・ドップラー・レーダーで、低空や地上の敵目標を探知可能なルックダウン能力を持つ。 その後、米空軍は1995年までに2,795機のF-16を導入し、極東でも韓国駐留第8戦術戦闘航空団へ48機(1981年)、および1985年から青森県三沢基地に駐屯する第432戦術戦闘航空団傘下で2師団(定数48機)が編成された。NATO4空軍は1992年までに515機を調達した他、イスラエル、エジプト、パキスタン、ベネズエラ、韓国、トルコ、ギリシャ、シンガポール、タイの各空軍がF-16を採用、導入している。
 |