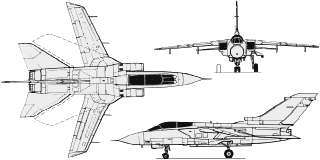
パナビア・トーネードは実用機として最小の可変後退翼戦闘機であり、米海軍がF-111の苦い経験を活かして軽量化に努め開発したF-14 トムキャットより自重で25パーセント、全長、全幅ともはるかにコンパクトな設計だ。 1968年、イギリス政府の提唱で始まったトーネード開発プロジェクトは、当初イギリス、西ドイツ、イタリア、オランダの4カ国が参加し、その後オランダは脱落する。結局、残る3カ国でパナビアという会社が設立され、開発へ参加したのは主にBAE(イギリス)、MBB、VFW(西ドイツ)、アエリタリア(イタリア)と3カ国4社で、機体の生産もこれら4社が分担した。 トーネードは計画名称をMRCA(多任務戦闘機)と呼ばれるとおり、低空侵攻、対艦攻撃、制空、要撃など多くの任務を要求され、F-111が低空侵攻(米空軍)および艦隊防空(米海軍)という2つの任務を両立できなかったことを思えば、トーネード開発の苦労は想像できよう。 トーネ−ドが基本設計で要求されたのは、多くの任務をこなせる多機能システム以外、敵のレーダーに捉えられない小さな投影面積とSTOL性能だ。機体をコンパクトにまとめるため、小型で高推力のエンジン(RB199)が不可欠であり、燃料タンクを大きく取れない制約から燃費も低く抑えなくてはならない。しかし、トーネードが要求される低空侵攻は多量の燃料を消費してもおかしくない飛行条件なのである。 こうした厳しい要求に加え、さらに敵の第1撃で主要基地が破壊されても出撃できるようSTOL(短距離離着陸)性能を求められた。その結果、採用された可変後退翼ながら、このピポット機構は優れたSTOL性能の一方で重量増加を誘う。これもジレンマの1つだ。 主翼へ前縁スラット、後縁へダブルスロッテッド・フラップと、可能な限りの高揚力装置が付けられ、上面には横操縦と着陸後の制動を兼ねたスポイラー、その上、尾部上面へ2枚のスピードブレーキがあるばかりか、戦闘機としてはスウェーデンのJA-37 ビゲンしか例のない逆噴射制動機構まで持つ。これだけ付ければ制動用パラシュートがなくても着陸滑走距離は最短で356メートルというから驚くべき性能だ。また、離陸滑走距離も700メートルと短い。 武装は機首に27mm口径のマウザー砲2門を固定装備し、胴体下部と主翼下7ケ所のハードポイント(兵装搭載箇所)へ9トンの外部兵装が積める。トーネードは基本的に攻撃型(IDS)と全天候迎撃型(ADV)があり、それぞれ複座配置でも細かい仕様は違う。 攻撃型は慣性航法装置、ドップラー・レーダー、地形追随装置と自動操縦装置を持ち、低空飛行が可能だ。F-104Gの後続機として、西ドイツ海軍は112機、西ドイツ空軍は212機、イタリア空軍は100機の攻撃型を採用し、また、イギリス空軍もトーネードGR1の名称で220機の攻撃型をバッカニア攻撃機の後続機に採用した。 イギリス空軍がトーネードF2として165機を導入した全天候迎撃型は、71cm延長された機首へ探知距離180kmのフォックスハンター・レーダーを納め、胴体下部にスカイフラッシュ空対空ミサイル4発を半埋め込み式で装備する。27mm砲1門を降ろし、燃料容量が増やされているのは、その任務の性格からだ。1985年オマーンが12機、サウジアラビアが72機の全天候迎撃型を発注した。
 |