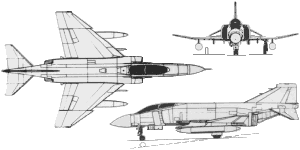
折からのベトナム戦争で大増産され、米海軍、海兵隊に続いて米空軍が採用した他、英海空軍、西ドイツ、ギリシャ、スペイン、イラン、サウジアラビア、エジプト、韓国、イスラエル、そして日本の航空自衛隊もF-4EJを採用国産化した結果、総生産機数は5,195機と、西側のジェット戦闘機史上F-86セイバーに次ぐベストセラー機である。 米海軍の要求から生まれたF4H-1(F-4A)がF-4B、F-4J、F-4N、F-4Sと発展し、空軍ではF-4Bを陸上仕様へと改めたF-4CからFー4D、さらに20mm口径のM61バルカン機関砲を機首に固定装備したF-4Fへと発展する。英海空軍も国産の採用を諦め、F-4ファントムにロールスロイス社製スペイ・ターボファン・エンジンを積むことで面目を保ちながら、F-4Kを英海軍がファントムFG1、F-4Mを英空軍がファンタムFG2の名称で採用した(後に英空母の退役で、ファントムFG1は英空軍へ移管される)。 日本の航空自衛隊が、その5師団用に139機のF-4Eファントムを注文したのは原型の初飛行から10年を経た1968年のことで、1971年に最初の2機が納入された後は名古屋の三菱重工で126機がライセンス生産された。F-15Jの導入後は主力戦闘機の座を下り、110機が攻撃機、17機が戦略偵察機へ改造され、APG-66J火器管制レーダーなどの近代装備を施された前者は1984年7月、後者は1992年に初飛行を行う。 本来の高性能に加え、こうして広く行き渡れば互換性の上でも有利となり、戦闘以外の任務を持つ派生型が生まれるのは自然の成り行きだ。写真偵察機として米海兵隊向けのRF-4B、米空軍向けのRF-4Cと、その発展型であるRF-4Eの3機種が製造され、F-4Eを原型にした電子戦、レーダー・ステーション攻撃機F-4Gもある。 原型のF-4Aは、もともと艦上戦闘機として開発された。機首に大型のAPG火器管制レーダーを持ち、胴体下部へはスパロー空対空ミサイル4基が、その後の戦闘機で標準となった半埋込み式に装備できる。火器管制装置を積むため複座のF-4Aは、それまでの戦闘機と比べ、異例の大型機でもあった。空母着艦の厳しい制約から、高揚力を獲るため主翼前縁のスラットや後縁のフラップへ加えてBLC(吹き出しフラップ)を採り入れ、また尾部には高機動中スピンからの回復でも効果がある陸上着陸時の制動用ドラッグシュートを持つ。 ジェネラル・エレクトリック社のJ79ターボジェット・エンジンを双発配置した合計推力はアフターバーナー使用時で16tを超え、機外のハードポイント(兵装搭載箇所)5カ所へ豊富な兵装が搭載可能だ。そのパワーと柔軟性は、新しく開発された誘導爆弾、空対地ミサイル、赤外線やレーザー照準装置などの追加装備をするにも、うってつけであった。 ベトナム戦争が実戦のデビューとなり、米海軍のF-4B/Jはトンキン湾上の空母から、また米空軍のF-4C/D/Eはタイおよび南ベトナムの基地から発進し、北ベトナムの爆撃やその護衛に向かう一方、南ベトナムの基地で駐屯する米海兵隊のF-4B/Jが、もっぱら南ベトナム国内の共産軍攻撃を繰り返す。主力戦闘機の座を確保した米海空軍のF-4B/C/D/E/Jだけで、ベトナム戦争中、北ベトナム軍所属のMiG-17/19/21を140機半撃墜し(半は他の機種との共同撃墜)、これはベトナム戦争全期間中、米軍が撃墜した記録の74パーセントに及ぶ数字だ。 続く戦場は中東へ移り、1973年の第4次中東戦争で被占領地奪回を目指すシリア、エジプト軍の攻撃を受け、F-4Eファントムを装備したイスラエル軍は、空対地ミサイルを含む米政府の支援を受けて反撃を開始、これらのミサイルがMiG-21の撃墜に大きく貢献する。また、イラン・イラク戦争でもF-4Dファントムは前線へ駆り出されるが、この時は両国間にまたがる広い砂漠が災いし、両軍の戦闘機は交戦する機会がないまま終わった。
 |